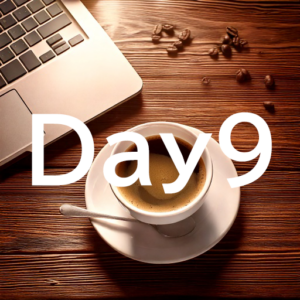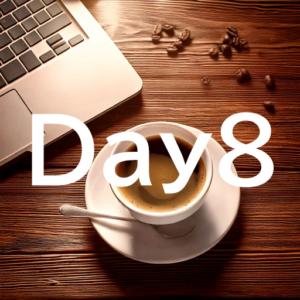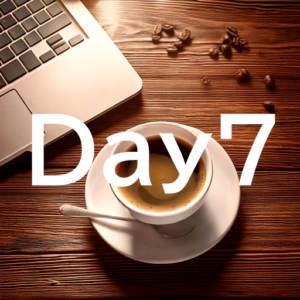なぜ今、データエンジニアという職種を選んだのか?
私は、未経験からITの世界に飛び込むにあたり、数あるエンジニア職の中でも「データエンジニア」を選びました。
その理由は大きく3つあります。
①社会的ニーズの急拡大と将来性
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの活用が進む中で、
あらゆる業界が「データを活用した経営・業務改善」に取り組み始めています。
しかし、その前提となる「使えるデータを整える工程」に課題を抱える企業はまだまだ多く、
データエンジニアのスキルはこれからますます重宝されると感じています。
医療・介護・行政といった分野でも、正確かつ再利用可能なデータ基盤が整っていないケースが多く、
私のように現場を理解できる人材が、“橋渡し役”として貢献できる余地が非常に大きいと実感しています。
② 自分の得意分野と強くリンクしている
私は、もともとPC操作やデータの整理・構造化が得意で、楽しさを感じるタイプです。
看護師として働く中でも、手順の最適化やマニュアルの整備、情報の共有フロー改善など、
「現場の効率を上げる仕組みづくり」にやりがいを感じてきました。
データエンジニアリングは、まさにその延長線上にあるスキルだと思っています。
「現場に役立つ仕組みを構築する」ことで間接的に多くの人を支えることができる、この点に強い魅力を感じています。
③ 分析や意思決定支援にもつなげていけるキャリア
データエンジニアは「整える」役割ですが、その先には「分析」「提案」「改善」へと繋がる世界があります。
私は将来的に、単に処理するだけでなく、データから価値を引き出す役割(=サイエンティスト的な視点)も担っていきたいと考えています。
まずはデータの構造・加工・流通に強いエンジニアとして実績を積み、
いずれは「課題を発見し、データで証明し、改善策を提示する」ような存在になれればと思っています。
自分の経験がどうデータエンジニアリングに活かせるか
私には、看護師として現場で働いてきた経験があります。
この経験は、単なる医療知識だけでなく、「現場のニーズを正しく汲み取り、必要な情報を整理する力」を育んでくれました。
データエンジニアとして求められる要件定義やデータ設計において、この実践力は強みになると考えています。
また、医療情報技師としてシステムやITインフラにも関わってきたことで、
データ構造や情報の流れを技術的な視点で理解する基盤も築くことができました。
これは、クラウド環境やDWH設計といったデータエンジニアリングの実務にも直結するスキルです。
さらに、私はもともとPCやデータ処理に対して興味があり、新しい技術を自分で学び、使いこなすことに楽しさを感じるタイプです。
この「好き」という気持ちは、継続的な学習や成長の土台になると実感しています。
どういった業務に関わっていきたいか
まずは、ETL処理やデータウェアハウス(DWH)構築といったデータ基盤の整備から業務をスタートし、
データを「使える状態に整える技術」を着実に身につけていきたいと考えています。
その後は、分析や可視化にも関わり、意思決定を支援できるデータ活用の提案まで行える人材を目指します。
単なるシステム構築にとどまらず、データからどのような価値が導き出せるかを考える視点も磨いていきたいと思っています。
また、将来的にはコンサルティング的な視点も身につけ、技術者としてだけでなく、
クライアントと同じ目線で課題に向き合い、「実装+提案」の両面から支援できるパートナー的存在を目指したいと考えています。
医療現場で感じた課題とデータ利活用の気づき
データ利活用に強い興味がある理由
私は看護師として、患者さんへの直接的なケアと、電子カルテなどへの間接的な記録業務の両方に携わってきました。
現場では、こうした記録業務の比重が大きくなり、「患者さんと関わる時間が少ない」と感じることも多くありました。
実際、患者さんの側から見ても「看護師と話す時間が少ない」と不満に感じている方も少なくないと思います。
最近では、病院でも業務の効率化だけでなく、患者満足度の向上にも力を入れるようになってきています。
しかし、ここにはジレンマがあります。
業務の質を高めようとすると、どうしても効率化が求められ、患者さん一人ひとりにかける時間が減ってしまう。
一方で、満足度を上げようとすれば時間が必要になり、業務が滞りやすくなる——このバランスは非常に難しいものです。
看護師の経験やスキルである程度補える部分もありますが、患者さんの感じ方によって満足度に差が出てしまうことも多く、属人的になりがちです。
そこで私は、電子カルテなどの記録業務を効率化し、患者さんと向き合う時間を増やせるツールや仕組みがあれば、看護師・患者さん双方にとって大きなメリットになるのではないかと考えました。
実際、医療現場では多くのデータが蓄積されています。
だからこそ、そのデータを整理・活用することで現場の課題解決に繋げる必要があると強く感じています。
データを活用することで、現場を支える力になると実感した
病棟で勤務していた頃は、日々の患者対応に追われる中で、データを活用する余裕はほとんどありませんでした。
目の前の業務をこなすことで精一杯で、記録や報告が「負担」として感じられることも多かったです。
しかし、異動後に配属された材料部では状況が一変しました。
そこでは、マニュアル整備や物品データの管理といったバックオフィス業務に集中できる環境が整っており、データを活かすことで業務を効率化し、現場を支える実感を得ることができました。
具体的には、以下のような取り組みを行いました:
1. 品質と業務効率の向上
- iPadの導入により紙マニュアルを廃止し、常に最新の手順を共有
- 経験やスキルの差によるミスを防ぎ、教育の標準化と効率化を実現
- バリデーションやチェックリストを通じて、データに基づいた品質保証体制を構築
2. データドリブンな業務改善
- 滅菌履歴データと医療器具データを突合・可視化し、インシデントリスクの低減につなげた
3. 紛失防止への取り組み
- 医療器具の紛失状況をデータで集計し、傾向と原因を分析
- 対応策を院内QC活動で提案・実行し、器具紛失率を5%削減する成果を達成
4. リーダーシップとIT活用推進
- 複数部門との連携をリードし、チーム内外の業務改善を推進
- ITに不慣れなスタッフへのサポートも積極的に行い、チーム全体でのIT活用文化を醸成
これらの経験を通じて、私は「データを整え、見える化することで、現場全体の質が向上する」という確かな手応えを感じました。
現場で働くスタッフの手間を減らし、間接的に患者さんの安全・満足度向上に貢献できる。
このような“裏方として支える役割”が私のやりたかったことであり、そこに大きな価値があるのだと実感しました。
「現場で使えるデータ・仕組み」をつくる側に回りたいと思うようになった
近年、看護業務において電子カルテは欠かせない存在となっています。
しかしその一方で、現場の使いやすさが十分に考慮されていないケースも多く、システムが業務の妨げになっている場面にもたびたび直面してきました。
例えば、入院時の記録では同じ情報を2重、3重に入力することが当たり前のようになっており、
加えて電子カルテとは別に紙媒体での記録・保管まで求められることがあります。
このような非効率な運用は、ただでさえ忙しい現場の業務負担をさらに増やし、
結果的に患者さんと向き合う時間を圧迫している大きな要因のひとつだと感じています。
また、システムそのものの設計についても、「現場が本当に求めていること」と「実際に提供される仕組み」との間に大きなギャップがあることも少なくありません。
この乖離の背景には、クライアント(医療者側)とベンダー(開発側)の間に立ち、相互理解を橋渡しできる存在が不足しているという構造的な課題もあると考えています。
こうした経験から私は、
現場のニーズを理解し、業務に本当に役立つ仕組みやデータ基盤をつくる側に立ちたいと強く思うようになりました。
看護師としての経験を活かし、「医療の現場で、使いやすく、価値のあるシステムをつくる」ことができるエンジニアを目指しています。
今後の方向性と学びの軸
現在私は、「技術 × 課題解決」という軸を大切にしながら、日々の学習と実践に取り組んでいます。
単にツールや技術を習得するだけではなく、
“誰の、どんな困りごとを解決するのか”という視点を常に意識するようにしています。
今後は、現場のリアルを理解しているからこそできる
「現場に即したデータ整備力」と、分析・可視化・提案などを通じて「ビジネスや社会に貢献できる視点」の両立を目指していきたいと考えています。
そして、より多くの人の意思決定や行動を支える、
価値あるデータ活用の土台を築ける人材になれるよう、
今後も実務と学習を重ねながら、
社会や現場の課題解決に貢献できるデータエンジニアを目指して、挑戦を続けていきます。

データの利活用等で人を支える役割が好きなんだなと再認識しました!